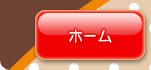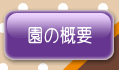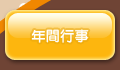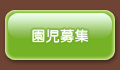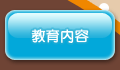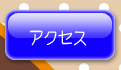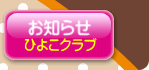一日の流れ(ある日の雁の巣幼稚園)
| 時間・園児の活動 | 園児の様子 | ||
<登園> |
 |
門までお家の人と手を繋いで来たら、ここで「いってきます」をします。園長先生に「おはようございます」のあいさつをして、優しい先生やお友達の待つ保育室へ向かいます。 | |
<好きな遊び> |
 |
教師が用意した環境の中で、子どもは自発的に遊び、遊びの中から様々なことを学んでいきます。「○○ちゃん、一緒に遊ぼう」「先生、見て!」など、友達や教師とかかわりながら、それぞれの興味・関心に沿って遊びが展開していきます。 | |
<みんなで遊ぼう> |
 |
クラス全員で歌を歌ったり、ハサミやパスを使って製作をしたり、簡単なルールのある遊びをしたりします。先生の話を聞いて理解する力や、作品を通して表現する力などが育つ時間です。 | |
<お弁当> |
 |
雁の巣幼稚園では週4回のお弁当全てがお家の人の手作り愛情弁当です。お家の人だから分かる、好きな物や食べる量。子ども達はお弁当の時間を毎日楽しみにしています。「おいしい!」と、とっても嬉しそうな子ども達です。 ※水曜日は午前中保育のため、お弁当はありません。 |
|
<好きな遊び> |
 |
午後にも遊ぶ時間があります。お昼も食べて、元気いっぱい!固定遊具に挑戦したり、鬼ごっこなどで身体を動かして遊ぶ子どもが大勢います。 | |
<帰りの集まり> |
絵本を見たり、今日一日の出来事を振り返ったり、明日ことについて先生の話を聞いたりします。「また明日も○○したいね」などという声が聞こえてきます。 | ||
<降園> |
 |
降園時は担任の先生と一人一人「さようなら」をして帰ります。毎日お家の人がお迎えに来ることで、幼稚園のこと、友達のことがよく分かり、安心して通っていただくことができます! | |
特色のある教育
| 祖父母参観 | ||
|---|---|---|
| 七夕会・焼きいも会・豆まき会の年3回、園児の祖父母を対象とした参観があります。 ※祖父母参観参加者の声(別ページが開きます) | ||
  |
||
| 雁の巣太鼓 | ||
| 平成22年度より、年長組が「雁の巣太鼓」として、竹太鼓、和太鼓にチャレンジしています。 教師や友達と一緒に頑張ったことを通して、協力・団結することの心地よさを味わい、最後までやり抜くことの大切さを学んでいきます。 |
||
 |
||
| スマイルタイム | ||
| ニュージーランド出身のセイディ先生から、英語の歌やゲーム、絵本の読み聞かせをしてもらい、外国の方とコミュニケーションをとる楽しさを味わっています。 | ||


|
||
| 縦割り保育 | ||
| 年数回、「縦割り保育」として、クラスをばらした異年齢グループでの保育を行っています。3歳の年齢差は、成長のステップを感じさせ、年長組がリーダーとなって、お弁当や遊びのお世話をしてくれます。担任以外の教師との出会いも良い体験となっています。 また、「縦割り保育」の他にも、園外保育や遠足に行くときは、年長組と年少組が手をつないで歩きます。そうすることで、年長児には小さいお友達に親切する態度が、年少児には年上のお友達を尊敬する態度が自然と身についていきます。 このような異年齢児の交流は日常の遊びの中でもごく自然に見られ、人との関わり方を知り、思いやりの心を育むことにつながっています。 | ||
 
|
||
| 自然とふれあう | ||
| 園内外の恵まれた自然環境を活かし保育に取り入れています。 6月には奈多海岸へ、10月は雁の巣レクリエーションセンターに園外保育に出かけます。 |
||
 
|
||
園児数(H29年4月1日現在)
※雁の巣幼稚園は平成31年3月に閉園する事が決まっています。今年度は年中・年長の2学年,来年度は年長のみの1学年になります。
| クラス | 在園児 | 定員 |
| 年中4歳児(ちゅうりっぷぐみ) | 35 | |
| 年長5歳児(ゆりぐみ) | 35 | |
| 計 | 70 |
お気に入りの場所
| 保育室内の環境 | |||
| 子どもたちの初めての作品を飾りました。 ちょうちょにシールを貼って飾りをつけ、クレパスで模様を描きました。 壁に飾った自分の作品を見た子どもたち、「私のちょうちょだ」「おさんぽしてる」「たのしそう」 「私のはどこかな?」などと言って喜んでいました。 |
|||
 |